

冬の京都「親子旅」
2月10日〜12日の三連休を利用し
冬の京都を「親子旅」しようと話が決まる。
娘婿が「レンタカーを運転する」と言ってくれたので
レンタカーを使って京都気まま旅という事になる。
ちょうど、長女の誕生日、
誕生祝を兼ねての旅でもある。
「2月10日」
12時30分、JR京都駅集合

「京都タワー」は補修中
全員集合

総勢5人が勢揃い
京都観光名所案内図

観光地図を囲んでワイワイガヤガヤ!
昼食は「おめん」という店を予約してあるとの事。
「おめん」が最初は何の事か分からなかったが、
漢字で書くと「御麺」
分かりやすく言うと、「うどん屋さん」ということである。
2時少し前に店に到着。
店の前には、外国人も含め長い列が出来ている。
30分から1時間は待たなければという。
我々は予約してあったので、即食事にありつけた。
うどんも美味しかったが、薬味・だしが抜群。
それと共に、お店のホームページも一見の価値あり。
http://www.omen.co.jp/index.html
昼食後
近くの、「南禅寺」を拝観する事にする。
南禅寺の詳細はウェブリアルバムでご覧下さい。
このアイコンをクリックで  アルバムが開きます。
アルバムが開きます。
F11キーをクリックすると「フルスクリーン」でご覧になれます。
南禅寺拝観後ホテルに向かう。
三連休の初日。ホテルは何処も満室。
インターネット検索一時間半。やっとキャッチできたホテル。
中京区の「ホテル杉長」
ホームページには「受験生のホテル」と書かれている。
京大受験生などのお宿になったのであろう。
夕食は外に出て「豆屋源蔵」で頂く。
大仏次郎、井上靖、ドナルド・キーンなど著名人が愛用した店。
町屋作りの細長い建物構造が、京情緒を奏でる。
豆屋源蔵「鴨川コース」
 |
 |
|
| 市役所のイルミネーションが美しい | 古風な暖簾 | |
 |
 |
|
| 先付け(湯葉豆腐) | 前菜(季節の五種) | |
 |
 |
|
| 吸い物(すっぽん豆腐・白髪葱添え) | 造り(鯛とひらめ) | |
 |
 |
|
| 焼き物(鰆味噌柚庵焼き) | 温物(碗豆腐 花麩 葉山葵 銀餡かけ) | |
 |
 |
|
| 酢の物(のれそれ土佐酢和え 絹豆腐 引き上げ湯葉 水玉胡瓜 独活 花穂紫蘇) |
飯物(豆ご飯・ちりめん山椒) 汁物(赤だし) 香物 |
アルコールも頂きながら、
料理の運ばれるテンポに合わせ
ゆっくり家族で語り合った
楽しい夕食であった。
![]()
「2月11日」
まず「高台寺」を訪れる。
秀吉の妻「ねね」が、自分の終の棲家とすると共に
夫秀吉の菩提を弔う為に建立。
北政所は後陽成天皇より、「高台院」の号を勅賜される。
寺の名前も「高台院」にちなんで「高台寺」と命名。
徳川家康は「高台寺」建設には、充分な援助をしたといわれている。
高台寺境内マップ
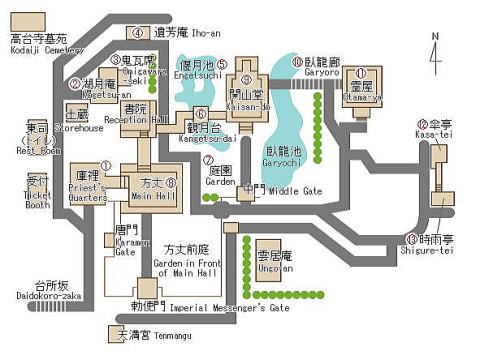
高台寺に入ってまず目に付くのが「庫裏」の前に立つ表札。
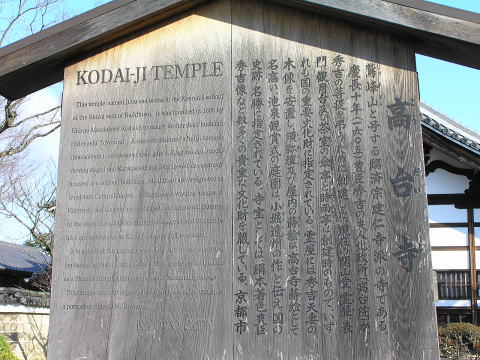
ここから、高台寺の拝観が始まる。
「高台寺」の内部も、ウェブリアルバムでご覧下さい。

このアイコンクリックで、アルバムが開きます。
F11キークリックで、フルスクリーンになります。
![]()
引き続いて、「竜安寺」を訪れる。
竜安寺は「石庭」として有名。
この庭を拝観した、エリザベス女王が絶賛した事から
日本国内は勿論、世界各地の人の注目を集めている。
いつ行っても、外人の姿が多く。
多くの人は「石庭」を前にして座り込み、沈思黙考している。
日本人以上に、熱心に東洋の神秘を味わおうとしている。
制作年代、制作者、製作意図のいずれも明確でなく
なぞの多い庭園である。
虎の子渡し・七五三の石組・黄金分割・バースペクティブ
などさまざまな説が唱えられている。
竜安寺 山門

禅宗寺院らしい佇まい
庫 裏

坂を上り詰めた所に「庫裏」がある。
切り妻作り、本瓦葺き、妻入り形式。
ミニチュア

庫裏と方丈の廊下に箱庭式の「石庭」ミニチュアー
「石庭」全景

油土塀を背景に、幅25m、奥行き10mの庭。
左半部 右半分


古文書に描かれた「石庭」
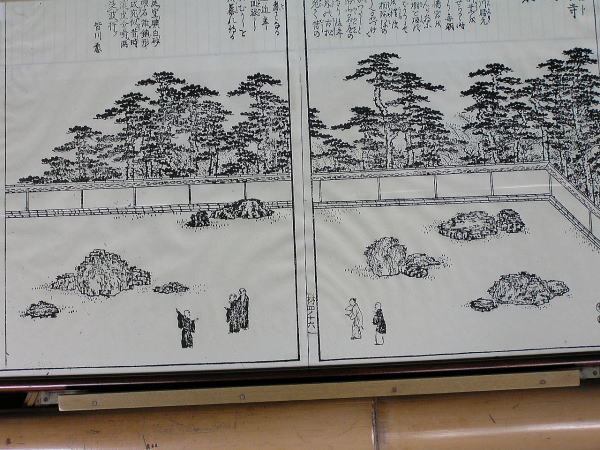
庭に入って見ることが出来たようです。
石の大きさ、配置が少し変わっている。
満 席

あまりお行儀が良くないようですね!!
”石が全部で15個あるはずだ”といって走り回っている人もいた。
垂木の反り

ホンの少しの垂木の反りが、柔らかい美しさを醸し出している。
油土塀の裏側

菜種油を練りこんである強固な土塀。
つくばい

徳川光圀が寄進したといわれる「つくばい」
中央の口を共用すれば”吾れ唯だ足るを知る”と読める。
釈迦の教えの根本を表している。
鏡 容 池

昔はおしどりが遊んでいたので”おしどり池”とも呼ばれる。
![]()
この後「妙心寺」を訪れる。
妙心寺については、私のホームページで既に報告している。
妙心寺 http://kangawa-id.hp.infoseek.co.jp/newpage40.htm
ここでは、妙心寺の塔頭である「大通院」についての写真を掲げる。
大通院山門

拝観は出来ない。
苑 内

整然と整った園庭
掲 示 板
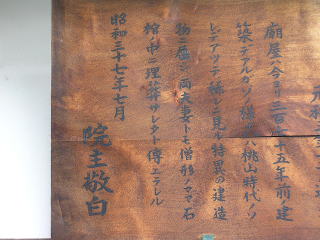
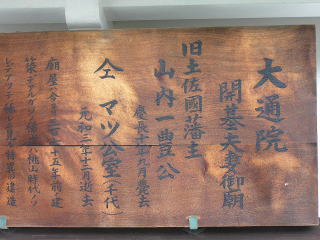
僧形のまま石棺の中にに埋葬と 一豊とマツ(千代)の廟である
![]()
昼食後まず「化野念仏寺」(あだしの念仏寺)を訪れる。
墓を作る事の無かった昔、死人は山裾に放置された。(風葬)
京都では、東山の五条から清水坂辺りとこの嵯峨周辺がその地であった。
今から1100年ほど前、野ざらしになっていた遺骸を埋葬し石仏を立てた。
その石仏もあだし野一体にsんランしていたのを、
明治中期に地元の人の協力で一箇所に集めた。
これが念仏寺の始まり。


長い石段を登る 虫の墓(虫塚)まである


仏塔(三重塔・五重塔の原型) インド風の鳥居








合 掌
![]()
ついで、本日最後の「嵯峨野散策」となる。





写真を並べてみると、垣根の持つ意味が良く分かる。
![]()
「2月12日」
最終日は「宇治方面」ドライブ旅行となる
まずは、「宇治平等院」に向かって出発。
「平等院」は、現在大修理中。
本堂には天蓋も光背もなく、本尊「阿弥陀如来」がポツンと
飛天も多くは修理中である。
平等院伽藍配置図

鳳凰堂と鳳翔館が必見
斜めから見た鳳凰堂(国宝)

古色のある鳳凰堂
阿字池の写る鳳凰堂

快晴・無風の為、逆さ鳳凰堂が見られた。
鳳凰堂正面

真正面から鳳凰堂を見る。
阿弥陀如来(国宝)のお顔

池越しに、10倍ズームでやっと阿弥陀如来のお顔が撮影できた。
屋根の上の「鳳凰」


左右の鳳凰が10倍ズームでやっと撮影できた。
今、屋根の上にあるのはコピー。
本物(国宝)は、鳳翔館で展示中。
NHKきんきメディアプラント大阪芸術大学の共同研究で
鳳凰堂がCGによって創建当時の色彩を取り戻した。
CGの映像は、「ウェブリアルバム」に収めました。
下のアイコンをクリックすると見れます。

F11キーをクリックするとフルスクリーンで見る事ができます。
宇治川

宇治川の流れは思いの外激しい。
鵜

鵜飼をする為の「川鵜」が飼われている。
凄く厳しい臭いがする。
![]()
宇治の帰りに「伏見稲荷大社」にお参りする事にした。
三連休なので少しは人が出ているか?
と思って行ったら、物凄い人出。

参道は人で溢れている。
鳥 居

大きな「稲荷型鳥居」
楼 門

どっしりとした楼門
以下、写真でご覧下さい。







![]()
京都最後の拝観場所は「東 寺(教王護国寺)」
東寺にある国宝は、五重塔を始めとして21点。
重要文化財に至っては数え切れないほどである。


五重塔(国宝)

国宝「東寺 五重塔」
日本の五重塔の中でも最大(54.8m)
均整の取れた、安定感のある五重塔


回廊の中間部分に注意! 軒を支えるのは「天邪鬼」 その理由は??
東寺 金堂(国宝)

東寺 金堂 本尊は、薬師三尊(重文)

薬師三尊(国宝)
金堂アップ

扉を開くと本尊のお顔が拝める。
そのため、屋根を切り取り、一段と高くしている。
東寺 講堂(重文)

大日如来をはじめとする21体の密教彫像が所狭しと安置されている。
(立体曼荼羅)
その中の15体が国宝。

立体曼荼羅
ただただ、感動の数時間であった。
![]()
ここで、(冬の京都「親子旅」)も終了。
楽しく、家族の絆を強固にし、
歴史の勉強にもなった意義ある旅であった。
”ときどき、このような旅をしようね”
が最後の言葉。
お・わ・り