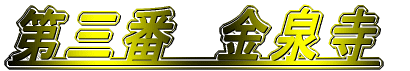
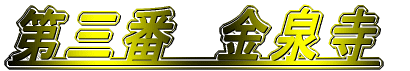

四国霊場八十八ヶ所 第三番 金泉寺
第一番と第二番は鳴門市大麻町、
「第三番 金泉寺」は板野郡板野町。

極楽寺から約2.5Km
歩き遍路では、車がブンブン走る12号線を歩くより
撫養街道又は遍路道を歩く方が味がある。

昔は小さな門前町があった。
橋を渡ると金泉寺の境内。
金泉寺のデータ
| 位 置 | 徳島県板野郡板野町大寺亀山 |
| 山 号 | 亀 光 山 (きこうざん) |
| 院 号 | 釈 迦 院 (しゃかいん) |
| 寺 号 | 金 泉 寺 (こんせんじ) |
| 本 尊 | 釈迦如来 |
| 宗 派 | 高野山 真言宗 |
![]()
![]()
弘法大師が通りかかったとき、
水不足で悩んでいるのを見かね井戸を掘った。
すると霊水が湧き出した。
そこで太子が堂宇を建て
それまで「金光明寺」と言っていたのを「金泉寺」と改称した。
![]()
屋島の壇ノ浦に向かう義経が、この寺に立ち寄って戦勝を祈願した。
その時、武蔵坊弁慶に大石を持ち上げさせた。
その成功で、全員が戦いへの意欲を高めた。
![]()
本堂の裏に長慶天皇陵と呼ばれるお墓がある。
長慶天皇が当寺で応永5年おなくなりになられた。
その後お墓の下から石碑が発掘され、天皇の御陵とわかった。
ただ、長慶天皇は謎の多い天皇。
南朝・北朝の関連もあり、墳墓の地も全国に存在する。
金泉寺へ

古い道標
門前町

昔は左右にお店があった。
古い門標

「阿波の青石」で作られている。
ここからは、ウェブリアルバムを借りて表示します。
このアイコン  をクリックしてご覧ください。
をクリックしてご覧ください。
なお、F11キーをクリックするとフル・スクリーンで見えます。
![]()
奥の院

第三番 金泉寺には「愛染院」という奥の院がある。

少し入り組んでいるが、撫養街道から少し北に入った所。

山 門

大きなわらじの付いた山門。
本 堂

こじんまりとした本堂。
本堂内部

提灯の紋が、不動明王の紋。
本尊の表示
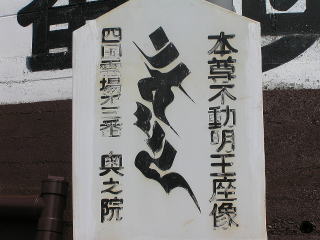
不動明王坐像と言うのは珍しい。(全国三例)
中央の梵字は、不動明王の「種字」
鐘 楼

不動明王にちなんで、鐘楼も真っ赤。
「赤沢信濃守」の墓所

板西城主「赤沢信濃守」の墓所
「赤沢信濃守」について
その当時、阿波の国は管領「細川家」が
勝瑞に城を構え治めていた。
中央では、織田信長が明智光秀に討たれるという大事変が起き、
四国では、長曽我部元親四国全土を席巻しようとしていた。
「赤沢信濃守」は板西城主として板野一帯を支配していた。
(板西城は、現在の板野町古城に城址がる)
長曽我部元親との戦いに降伏をせず、
戦いを挑んだ信濃守が敵将を討ち取らんとした時
「わらじの紐」がプツンと切れ、それが仇で敵将に討ち取られる。
そのため、腰から下の病気に良く効くと評判が広がる。
わらじの奉納

壁の内も外もわらじで覆われている。
赤沢家墓所

立派な墓所が作られている。
「刷毛書き」納経

四国で唯一「刷毛書き」で納経帳を書いてくれる。
珍しいので取材をさせてもらう。
刷 毛

硯箱の中には、何本かの刷毛筆。



完成! 納経帳
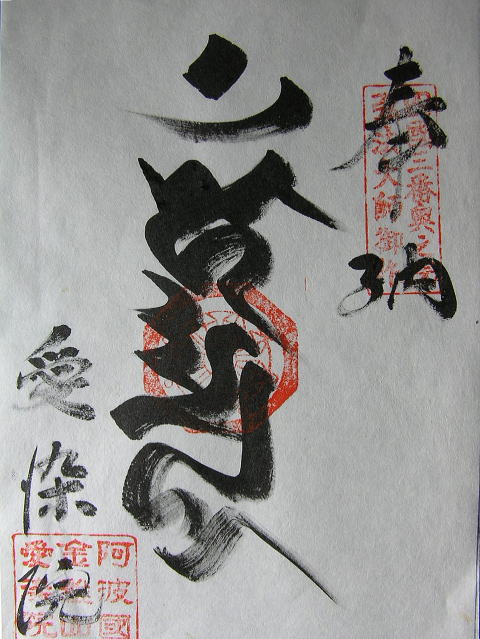
不動明王の「種字」以外は普通の筆で書く。
いかにも、梵字らしい味のある「種字」になる。
普通は梵字一字であるが、ここでは三字。

庭の片隅に、「ボタン」が一輪!
3月23日にしては珍しく早咲きである。
合掌
第二番 極楽寺 ![]()
![]() 第四番 大日寺
第四番 大日寺