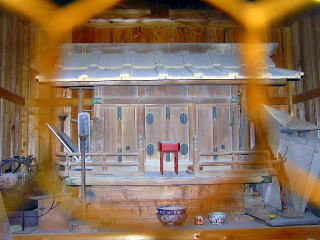「第十四番 常楽寺」から800m。
徒歩12分ほどで「第十五番 国分寺」に着く。
三寺配置図

寺域詳細

今では随分狭くなっている。
国分寺の由来
国分寺は聖武天皇が勅命により全国に建築させた寺。
「金光明四天王護国之寺」という僧寺と
「法華滅罪之尼寺」を建てるよう命じた。
「国分尼寺」は、国分寺からそれ程遠くない所に遺構がある。
当時の国分寺の規模は二町四方に及び、
七重の大塔を備えた大寺院であった。
しかし、
長宗我部によって焼き払われた。
その後1741年
藩の命令によって再建され現在に至っている
国分寺のデータ
| 位 置 |
徳島県徳島市国府町矢野 |
| 山 号 |
焼 王 山 |
| 院 号 |
金 色 院 |
| 寺 号 |
国 分 寺 |
| 本 尊 |
薬師如来 |
| 宗 派 |
曹 洞 宗 |
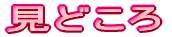
鳥瑟沙摩明王堂
「七重の大塔」礎石
山 門
本 堂
------------
山 門

橋を渡り、まず山門をくぐる。
この山門珍しい構造をしている


横から見ると、切り妻屋根の中心に柱が無く、柱が少しずれている。
作 図

図示するとこんな形である。
このような門の形を「薬医門」という。
四国八十八ヶ所の中では、珍しい門の構造である。
勅命寺院


聖武天皇の勅命によって建てられた寺院。
それなりに品格を備えている。
本 堂

重層入母屋造り、妻入り型の本堂。
規模は小さいが、構造的には「長野の善光寺」の様式。
ご本尊

行基菩薩作の「薬師如来坐像」
光背は後年の作か?
彫刻類と垂木構造






一層目の屋根と二層目の屋根では垂木の打ち方が違っている。
下の屋根は「平行垂木」 上の屋根は「扇垂木」
芯 礎

「七重の大塔」の芯となった礎石。
少し離れた、水田の中で発見された。
門・講堂・金堂が直線的に並ぶ様式をとっていた。
「七重の大塔」は、その線から外れ離れて建っていた。
鳥瑟沙摩(うすさま)明王堂

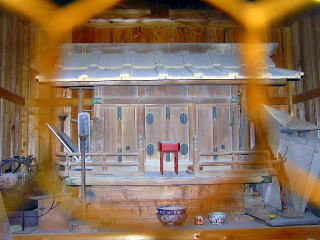
お堂の全景 内部の様子
この明王は一般にトイレの神様として信仰されている。
納経所で販売しているお札は、トイレに貼っておくと良い。
トイレに話題が移ったところでお開き!!
「第十四番 常楽寺」へ 
 「第十六番 観音寺」へ
「第十六番 観音寺」へ