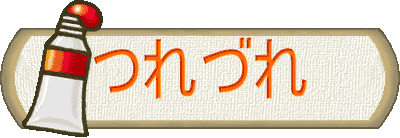
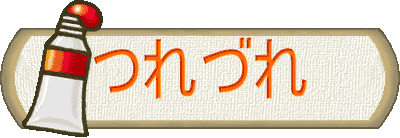
思いつくままに、在りし日のことを想い、動かぬ筆を運ぶ。
想いで多かりし日々。
悲しみのひと時。
懐かしい思い出。
心優しい人の事
多くの人に、 支えられ、 今日の日がある。
![]() 地名考
地名考
![]() 少年志願兵
少年志願兵
![]() フォートラン&コボル(コンピュータ悪戦苦闘記)
フォートラン&コボル(コンピュータ悪戦苦闘記)
![]() 子育て奮闘記
子育て奮闘記
![]() 私流 挑戦者たち
私流 挑戦者たち
![]() 生い立ちの記
生い立ちの記
![]() ビッグひな祭り
ビッグひな祭り
![]() 糖源境の八重桜
糖源境の八重桜
![]() 彩・恋・こい・鯉まつり
彩・恋・こい・鯉まつり
![]() 限りなき挑戦
限りなき挑戦
![]() レンコンの花
レンコンの花
![]() 打ち上げ花火
打ち上げ花火
![]() レンコン哀れ
レンコン哀れ
![]() レンコンその後
レンコンその後
![]() 元気高齢者問題
元気高齢者問題
![]() 河野メリクロン
河野メリクロン
![]() LEDイルミネーション
LEDイルミネーション
![]() 和三盆糖
和三盆糖
![]() 阿波は青石の国
阿波は青石の国
![]() ジャンボひな祭り
ジャンボひな祭り
![]() 田舎の戎っさん
田舎の戎っさん
![]() 妙心寺
妙心寺
![]() 湯村温泉
湯村温泉
![]()
![]() 日本一の山
日本一の山
![]()
![]() 芍薬の花
芍薬の花
![]()
![]() 大塚国際美術館
大塚国際美術館
![]()
![]() 鳴門花火大会
鳴門花火大会
![]()
![]() ガレの森美術館
ガレの森美術館
![]()
![]() 徳島陶芸家七人衆
徳島陶芸家七人衆
![]()
![]() 徳島の蘭展
徳島の蘭展
![]()
![]() グローバルビッグひな祭り
グローバルビッグひな祭り

![]() 地 名 考
地 名 考
私の生まれたところは、栄村の唐園(「とおのそ」と読む)と言う地名。
榮村と言う地名は全国いたる所にある、比較的新しい地名である。それに比べ
「唐園」と言う地名は珍しい。しかも、(とおのその)と読まないで(とおのそ)と読む
のもめずらしい。この唐園の中は、さらに二つの小字に分かれている。その一つは
香殿(こうでん)、もう一つは小原(おはら)。小原のほうはそれ程でも無いが、香殿
のほうは、日本の地名としては珍しい。
そのつもりで周辺の地名を調べると、すぐ隣の村は「矢武」(やたけと読む)。
少し山麓に近いところには「唐口」(とおのくちと読む)地名がある。さらに、山麓一
帯には「那東」(なとう)、「羅漢」(らかん)、「神宅」(かんやけ)などと言う、中国に
良くありそうな地名がある。
古い時代に、中国からの渡来人がこの近くに住み着いていた為に、このような
地名があるのではなかろうかと素人なりに推測する。
それに比べ、我々「寒川一族」がこの地に住み着いたのはまだ新しい。
古書によれば
寒 川 家(栄村)
祖先、讃岐の国寒川城の城主なりしが、天正年間長曾我部乱後、遺族阿波の国
板西郡唐園村に居住し田畑開墾を計り農事を指導する等・・・・・・
と記されているの。
祖先がこの地に来たのはたかだか天正年間のことである。
しかし、その時にはすでに多くの人がこの地に住み着き、生活を営んでいたと思わ
れるし、地名もその時にはすでについていたと思う。その地名の感じからすると
どうも中国系渡来人が、この近隣に散らばっていたのではないかと思う。
これは、資料や研究に裏打ちされたものではなく、感覚で言っているのではなは
だ怪しい。
いつかゆっくり調べてみたいものだと思っている。
始めに 戻る
![]() 少年志願兵
少年志願兵
太平洋戦争も末期に近づいた頃、「少年志願兵」と言う制度が出来た。
それまで、旧制中学校を終了した人で、優秀な人は海兵(海軍兵学校)または陸士
(陸軍士官学校)に進む人が多かった。また、短い上着に七つボタンの予科練習生
(予科練)も、若者の憧れであった。
それでも、若い兵隊が不足していたのか、中学校2年生から進む少年志願兵の
制度が出来た。その中でも、少年飛行兵が人気であった。両親にとっては、まだ子
供と思われる14歳の少年が、志願してお国の為と兵役に従事した。
この傾向は第2次世界大戦のアメリカでも見られた現象で、15〜6歳の若い人
が志願し兵士として前線に送られている。
幾らか、お調子者の傾向があった私は、この制度に便乗し、14歳のとき「少年
飛行兵」を志願し、検査に望んだ。学科試験は難なくパスしたが、飛行機酔いの検
査(イスに座り、頭を深く垂れ、イスを5〜6回回転し、止まると直立不動の姿勢で
立つ、と言う検査)で不合格となった。船酔い・飛行機酔いの傾向があり、航空機乗
務には不適切であると言うのであった。
ただ、理科系の試験結果が良かったので、最初の希望とは異なるが少年電探
兵(今で言えばレーダー兵)として採用されることとなった。
![]() 電 探 兵
電 探 兵
2年生も終わりに近い2月、歓呼の声に送られて入隊した。
入隊の場所は、神奈川県の藤沢市。そこに、海軍のレーダー兵訓練基地があった。
今までに、親の元を離れたこともない少年兵達が、全国から集まってきた。
最初の頃は、天真爛漫にお国言葉で会話が弾む。青森弁を話す戦友も居れば、熊
本弁で話す戦友もいる。かったるい京都言葉を話す者、チャキチャキの江戸っ子
弁でしゃべる者等で、意思の疎通がはなはだうまく進まない。そのうち、上官か
ら海軍言葉を叩き込まれ、一ヶ月ほどかかってようやく共通語で話すようになる。
軍隊での生活は想像以上に厳しいものであった。これは、苦痛であると言う意味
ではなく、凄い勉強量で、レーダーの専門知識の習得に、目が廻るような忙しさであ
った。
兵隊さんとしての訓練は殆んど無く、毎日が勉強勉強の連続。朝から夕方まで
「電磁気理論」「高周波発信」「電波伝送」「増幅回路」「アンテナ回路」等々、電気や
電波に関する勉強が目白押し。しかも使用する教科書は、いわゆる「赤本」。極秘
内容の為、持ち出しも貸し出しも厳禁。授業の前に配られ、授業が終わると即刻回
収。員数点検の後金庫の中へ・・・・。
ここで、電気に関する勉強をしっかりさせてもらった事が、後で随分役に立った。
「71歳のホームページ」を作ったりする根本は、この時に培われたのかもしれない。
![]() お寝小をする兵隊さん
お寝小をする兵隊さん
少年兵の生活は厳しいものであった。広大な敷地に錬兵場があり、その一隅に
兵舎がある。長い建物のが東西に建っており、その内部は端から端までが見渡せる
構造になっている。 今で言うオープンスペースの建築である。
建物内部の北側に土間の通路があり、南側は板敷きのワンフロアーである。南
の窓下に、個人のロッカーがずらりと並んでおり、中二階の部分はハンモック置き場
となっている。
私達は海軍に属しているので、船での生活を想定し、夜はハンモックで寝ること
になっている。夜、中二階からハンモックを下ろし、二列に並べる。ちょうど、木の枝
で、蓑虫が並んでぶら下がっているようになる。蓑虫は縦にぶら下がっているが、私
達は横に並んでブラブラ揺れている。
このハンモック、慣れるまで中々寝苦しいものである。
頭から足にかけて丸まっており、左右も同じように丸まっている。上に向いて寝ると、
左右の肩が上向きに丸められるので胸が圧迫され胸苦しくなる。勿論、横に向いて
寝ることは出来ない。横に向くと、背骨が横に曲げられ、寝られたものではない。
朝起床ラッパで起きるとそのハンモックを丸め、中二階に上げる。それを立てたま
ま並べ、班毎に城壁のようなものを作る。昔、東郷元帥が艦橋に立っている写真の前
に並べられているのがこのハンモックである。
同じ班の中に、お寝小をする兵隊さんが居た!。ハンモックは個人のものでなく、
彼のハンモックに誰が寝るようになるかは分からない。起床時には一斉に丸め、中二
階に上げ、夜は一斉に下ろして釣るので、次の夜、どれが誰に当たるか分からない。
湿ったハンモックに当たった戦友は、ブツクサ言いながらもそれに寝なければいけな
い羽目に陥る。
まるで漫画のような風景である。でも、その男勉強は良く出来た。
しかし、何故か、一番早く戦死してしまった。
![]() 最初の死の体験
最初の死の体験
6ヶ月間みっちり勉強をした後、7月、いよいよ前線に派兵される事となる。
私達の小隊は、洋上監視が目的である為、朝鮮半島に渡り、半島南部から玄
界灘の監視をする任務に就く。舞鶴港から機器一式を船に積み、朝鮮半島に
行くことになる。
貨物列車に機器を積み込み、兵も一緒に貨物列車に乗り、舞鶴港に向かう。
港では、すでに船が待っていた。、その船に機器を積み込んで港を離れた。
港を離れたと言うよりも、港を離れようとして湾口に向かっているとき、航路上に
日本の潜水艦がぽっかり浮かんできた。船は、急いで右に避けたが、避けた為に
機雷の掃海が出来ていない海域に出た。当時、日本の主要湾岸にはアメリカの
磁気機雷が沢山ばら撒かれていた。その磁気機雷の上を船が通ったのか、激しい
爆発音と共に船の船尾が大きく持ち上げられ、次いで、船尾からずぶずぶと沈み
始めた。
爆発の衝撃で、何人かの戦友は海面に投げ出された。また、船室で休んでい
た戦友の何名かが死に、何名かは顔や服を焦がした状態で飛び出してきた。
一番気の毒であったのは、一番底に居た機関兵である。機雷の直撃を喰らい、
ここでも何名か死者がでた。生き残った多く兵は、重油を頭から浴び、全身真っ
黒な姿で船底から這い出してきた。
そうしている内に船はどんどん沈んでいく。
「全員海に飛び込め」と言う命令で着のみ着のままで、どぼん、どぼんと飛び込
んでいく。感心したのは、飛び込む前に全員が靴を脱いできちんと揃えてから、
飛び込む。
靴なんか揃えなくても、どうせ海に沈むのにと思うが、皆んなが靴を揃えては
飛び込んでいく。常々の生活の中でのしつけの厳しさが、こんな所に現れるのか
と感心をする。
幸い、湾内であったのですぐに救助されたが、それでも仲の良かった戦友2名
を失う。爆発のとき何処に居たかが生と死を分けた。甲板に居たものは誰も死なな
かったが、船倉、それも後部船倉で休んでいたものが不運であった。
生きるか死ぬかは、こんな些細なところに分かれ目がある。
空 中 魚 雷
舞鶴で機器を失った我々は、それでも、なるたけ早く南朝鮮まで行かなければ
ならない。舞鶴の旅館で待機。そのうち、北朝鮮からの大豆を運ぶ船が出るので
それに便乗。
関門海峡は機雷が敷設されているので、日本海を大きく迂回し、北朝鮮の港ま
で行くことになる。
海軍の食事は、一般に豊かなものである。主食の米飯はお代わりこそ無いが、
アルミの茶碗に一杯あり、副食も二品付き、十分腹を満たすものであった。農家生
まれの私にとって、食後にデザートとして果物が付くというのは驚きであった程で
ある。
しかし、今回の船の中の食事は惨めなものであった。食事の量は少ないし、餅
米しかないというので、もち米のご飯を食べさせれた。初めてもち米ご飯を食べた
が実に食べ難いものであった。
日本海の航海もそろそろ終わりに近づき、水平線上に朝鮮半島が見え始めた
時、一台の飛行機が飛来した。最初は友軍機と思っていたが、それがソ連の飛行
機であると分かり、船の中は緊張する。
船はジグザグ航路を取ろうとするが、船体が大きい上荷物を積んでいない空舟。
喫水が浅いので方向転換がうまく出来ない。幾らか方向を変へたが、飛行機の敏
捷さには叶わない。一発の空中魚雷を船の横っ腹に喰らう。凄い水柱が立ち上が
り、しばらくすると頭上から滝のような水が落ちてくる。
幸い、魚雷は船の船倉部分に当たったので、この攻撃による戦死者は無かっ
た。しかし、船全体がへの字型に折れ曲がり、航行不可能となる。そのまま浮か
んでいると、陸地から味方の小さな船が迎えに来てくれた。
北朝鮮の港に着いた後、南下しなければならない。専用列車等無いので、民間
の列車に便乗して南下する。途中、強烈なニンニクの匂いとダニの猛攻を受けな
がら、ようやく目的地の「鎮海鎮守府」に到着。 一息入れる。
大 爆 発
鎮海について一週間ほど経った時、広島が「新型爆弾」の攻撃を受けたと言う
報道がある。良く分からないまま数日が過ぎる。その間これと言う訓練も無く、無
為の時間を過ごす。
そして、8月15日の日がやってくる。しかし、それ以前から「敗戦」の雰囲気は
感じられていた。我々は、大きな混乱も無く一日一日を過ごしていたが、上層部は
大変であったようだ。
敗戦後の韓国人は、思いもよらないほどの変わり様で、手のひらを返したよう
になる。上官達はだんだん浮き足立ってくる。韓国出身の兵に、ひどい仕打ちをし
た上官もいる。(韓国出身の兵が逃亡し、捕らえられ、叩き殺された)
一方、アメリカ軍は勝利者として、戦争の終わったこの時間を楽しんでいる。
港に、わが軍の「水雷艇」が一艘係留してあったが、それはアメリカ将校達のよい
遊び道具になった。女性を乗せ水煙を巻き上げながら、湾内を疾走する。轟音を
発しながら、飛ぶように走り回る。
一方、我々は戦後処理に追いまくられる毎日となった。
山の洞窟の中に蓄えてあった兵器・火薬・爆弾・魚雷・機雷等を、玄界灘に海上
投棄する作業である。
横穴に入り、火薬などを運び出す者。
それを船に積み込むもの。
船に乗って海上投棄に向かう者それぞれ分担して作業を進めていく。
しかし、洞窟から運び出すのは簡単であるが、洋上投棄をするのは容易で
はない。自然、岸壁には運び出された火薬・砲弾類が、山となっている。
海軍であるので、運び出されたものは、魚雷・機雷・爆雷・砲弾・機関銃弾・小
銃弾等の上に、黒色火薬が堤防のように積み上げられてきた。しかも、この黒色
火薬、箱が腐ってぼろぼろこぼれている。
そんな状態で、大爆発が起こった。
運び出された黒色火薬を、コトンと置いたのがきっかけで、黒色火薬が燃え出し
た。この火薬、密閉された中で点火すると爆発するが、オープンな所では、シュルシ
ュルと燃える程度。丁度、花火の燃え方に似ている。
消防隊が出、注水を始める。しかし、火は堤防のように積み上げられた黒色火
薬の箱に燃え移る。そうなると、火は大きく立ち上がり始める。その黒色火薬の堤
防の端は、機雷や魚雷の山に繋がっている。
全員作業をやめ、火事の行方に注目する。
私も、3人の戦友と共に、引き上げられているカッター艇に凭れ、わいわい言いながら
眺めていた。
そして、一瞬、大音響と共に大爆発が起こった。
短い時間の中で、3回の爆発音が轟いた。
私は、爆風で数メートル後方に吹き飛ばされた。
辺りには土煙が立ち込め周りが薄暗くなった。
私は、飛ばされ、軍馬用の干草を広げた上に落ちた。草の上だったのでので何の
怪我もなかった。
何分間かの失神の後気がつく。枯れ草を動かしてみる、ガサガサと音が聞こえ
る。耳は大丈夫。 恐る恐る目を開けてみる。 木の枝が、木の幹が見える。
目も大丈夫のようだ。でも、枝もたわわについていた葉っぱは一枚もついていない。
頭をもたげて周りを見る。あちこちから悲鳴が聞こえる。
隣にいた戦友を探す。少し離れたカッター艇の破片の中に友はいた。
大怪我を負っていた。
機雷の破片がお腹を突き通り、お腹に大きな穴が開いている。
ハラワタも吹き飛ばされ、お腹の中は空っぽ。
上から横から下から、血が噴出してくる。
急いで、着ていた作業服を脱ぎお腹に押し当てる。
荒っぽい応急処置である。
意識を喪っていた友が気づく。強烈な悲鳴を上げる。
でも、どうすることも出来ない。
そのうち、衛生兵が到着。ようやく担架に載せ病院へ。
私も付き添う。
しだいに気力を喪っていく友。
「痛い痛い」から「もう殺してくれ」祈るようにつぶやく。
しかし、それから4時間。
戦友はうめき続けながらも、生きていた。
映画で、一発のピストルの弾を体に受け即死する場面がある。
嘘だと思った。
少し落ち着いて考えた。
彼と私が、火災を見る位置を入れ替わっていたら、今頃どうなっていたか。
生と死の分かれ目は、そんな些細な所にある。
この大爆発の経験から、私の、死生観・人生観が大きく変わる。
爆 発 の 後
爆発後の悲惨さは筆舌に尽くしがたいものである。
爆発後、怪我をしなかった者が動員され、復旧作業に当たった。
私も無傷であったので、その作業に従事した。
まず、地表で転がっている死体を取り除くのが、第一の作業であった。
爆発直後であったので、どの死体も腐敗しては居なかった。もちろん、爆発の
衝撃を受けて死んだのだから、いたみは激しい。手・足が吹き飛んだ者、首が
千切れて無い者、頭蓋骨が割れ脳みそが、剥き出しになっている者。
など様々である。
血液を流し切った死体は、皆土気色になっている。その上、爆発の時飛び散
った土ほこりを被っているので、ほこりまみれの死体である。ほこりまみれの死体
を二人で抱きかかえ、車に運ぶ。
一番顔をそむけたのは、眼球が飛び出た死体であった。不気味と言うより異
常な恐怖感が襲ってくる。案外 綺麗だなー と思ったのは、剥き出しになった脳
みそである。 柔らかそうな、お豆腐のような感じの、ピンク色である。脳みそって、
こんなに綺麗なものかと感心する。
爆発現場には、直径15m、深さ5mのすり鉢型の穴が、3箇所空いており、
そこから飛び出した土砂が周囲100mほどの所にうずたかく積もっている。深い
所では、1.5mもある。
次の作業は、その土砂を取り除き、土の下に埋まっている死体を掘り出す作
業であった。毎日毎日、スコップで土砂を取り除く作業が続けられた。作業をして
いる者にも、しだいに疲れが見えてくる。
疲れてくると、人間の思考は鈍くなる。死体を扱う作業に、何の感情も起きなく
なる。機械的にスコップを動かし、出て来た死体を車に放り上げる。まるで、さつ
ま芋でも扱っているような感情になる。
しかし、4日目を過ぎるあたりから、掘り出した死体に、蛆虫がウジョウジョわ
いていた。この死体を扱うの時は、さすが胸が震えた。
集められた死体は荼毘に付される。
私は、小隊長から命令で、荼毘要員として火葬場に派遣される。
幅2m・深さ2m・長さ50m程の溝が掘られ、その中に薪が一面に敷き詰めて
ある。その上に死体をずらりと並べる、さらに、薪を上に載せ灯油をふりかけ、火
を点ける。一晩、火の守をするのが、与えられた作業である。
夕食と酒を与えられたが、とても食事をする気にはなれない。なるべく、火の燃
えているほうを見ないようにしているが、時々不気味な音がするので、どうしても目
が行く。
「パーン」という音は、熱で膨張したお腹が裂ける音。「ギギー」というのは、火
に炙られた死体が上半身を立ち上げたり、足を持ち上げる音。
そして、カニやエビを焼いたような臭いが、あたり一面に漂う。
頭髪の焦げる匂いも、嫌な臭いであった。
戦友の冥福を祈り、読経を始める老兵士も居る。
しかし、私達若い者は、ただ黙然と頭を下げるのみであった。
故 郷 へ
戦後処理に2ヶ月。11月上旬、いよいよ帰国の途に着く。
釜山港まで列車で移動、そこから貨客船に乗り込む。小さな船で、4艘が船団を組
み佐世保に向かう。貨客船に定員を無視して乗り込んだものだから、トイレ不足。
どうするのかと見ていると、1m四方の箱で、そこに穴のあいてるものを、船の甲板
から外に出し、ロープで縛りつけ、臨時のトイレ。吹きさらしの上、風向きによっては
下から吹き上げてくる、大変なトイレ。
玄界灘の、冬の海の荒々しさは話に聞いていたが、今は11月、それ程でもないで
あろうと思っていた。しかし、台風の余波を受けてか、大荒れに荒れる。
うねりの頂上に船が上がると、水平線の彼方まで見渡せるが、うねりの底に入ると、
何にも見えない。
最初はピッチングだけであったが、途中からローリングが加わる。船が左に傾く
と、左の舷側が海面に浸かり、船が右に傾くと、掬い上げた海水が甲板を左から右
に猛烈な勢いで流れる。船が右に傾くと右の舷側が海水を掬い上げ、左に傾く時右
から左に海水が濁流となって流れる。
甲板は、海水の往復で綺麗に洗われている。勿論、仮設トイレは使い物にならな
いので、早々に撤去。
甲板が荒れるので、船倉に入ろうとするが、階段入り口で異様な臭気に会い、急
いで撤退する。船内で、何十人かの人間が、船酔いの為嘔吐した臭気がむんむんし
ている。幾らか寒いがそれでも船内よりはましと、艦橋の下で夜を明かす。
翌日佐世保到着。検疫の後上陸。DDTを頭から浴びせられ、ほうほうの体で駅に
行く。駅前の露天で食べた、「芋がゆ」のなんと美味しかったことか。
列車を探し車中の人となる。といっても、ぎゅうぎゅう詰め。網棚の上で寝る戦友
も居る。それでも交代しながら、列車は「広島」に近づく。「新型爆弾」の威力はどの
ようなものか、興味深深。
新型爆弾投下から3ヶ月経過している。
広島が近づく。
なんと、広島駅の一駅手前から、広島駅の次の駅まで、見えるものは「一面の瓦の
海」。
その頃は、広い道路は通れるようになっているが、道以外は一面の瓦。
瓦でびっしり埋まっている。
所々に、小さなビルがあったり、土蔵があったり。後は何にも無く、水平線。
そして地面は、一面の瓦。街路樹も、庭に生えていたであろう木も、何にもない。
新型爆弾(原子爆弾)の威力を、まざまざと見せ付けられた。
広島から岡山、乗り換えて高松、高徳線で板野駅下車。いよいよっ故郷に近づく。
迎えも無いので、歩いて我が家に帰る。
家の近くまで来た時、知り合いのおばさんが「ああ、はるさん、も・ん・た・ん・で」(治
雄さんお帰りになったんですね の阿波弁)
この言葉を聞いた途端、「ああ、故郷に帰り着いた」と実感した。
母が畑から飛んで帰り、「お帰り」の言葉とともに、身ぐるみ全部剥がされた。
衣類は全部、母の手で熱湯消毒。シラミ退治である。兄が先に帰って時の経験で
ある。
ゆっくり家の風呂に浸かり、のびのびと手足を伸ばした時。
「ああ、俺は生きているんだ」と、実感する。それとともに、亡くなった戦友達のことが
走馬灯のように想い起こされる。
亡くなった戦友たちのためにも、生かされたこの命、思う存分生きていこうと決意
する。
この項、終了
始めに 戻る
フォートラン&コボル(コンピュータ悪戦苦闘記)
今から25年前、「情報処理中央研修」と言う名目で、コンピュータに接する機会
があった。 当時、私は鳴門市教育研究所に勤務していたので、こんな研修会にも
参加する事が出来た。
研修会は、開設まだ間もない学園都市「筑波」にある、文部省の施設で行われた。
研修期間も長く、14日間の研修であった。
当時の筑波は、まだ造成中と言ってよいようなもので、武蔵野の雰囲気のある
雑木林の中に、近代的な建造物がポツン・ポツンと建ち始めていた。
ゆるく波打つような起伏の中に、自然と調和するかのように、研究施設が作られて
いる。
この風景を見て、参加した者の中には、「これは島流しだなあー」と言う声が聞こえ
た。勤務の帰りに「赤ちょうちん」で一献召し上がるお方には味も素っ気もない風景
に写った事と思う。
翌日から研修が始まった。
文部省の担当官が、歓迎の挨拶と研修のあらましについて説明する。研修期間中、
我々をサポートしてくれる新任の課員が紹介される。
日本でも一流の大学を卒業し、本省入りしただけあって、どの人もどの人も、いか
にも秀才といった感じの青年である。
色白でハンサム、秀才の言葉そのまま絵に描いたような顔立ちの人ばっかりで
ある。
”うちの娘が、こんな人と結婚出来たら、いいだろうなあー” と、思う。
しかし、研修の内容は難儀なものであった。2〜3日たって分かったことは研修内
容の難解さよりも、こんなにも、手取り足取りしなければ働かない、コンピューターに
対する失望感と、これで本当に実用になるのだろうかと言う不安感、不満感であった。
プログラムを作る為のコーディングシートには、書く位置が厳密に指定されており、
決められた所にコマンドを書き入れないと、動いてくれない・・・・・と先生が言う。
書かれたコーディンシートをコンピューターにかけるには、更に、キイー・パンチャ
ーの作業を待たなければならない。そのため、自分の作ったプログラムで、コンピュ
ーターがどのように動くかを見ることは出来ない。
毎日、毎日、コンピューターがどのように動いてくれるのか分からないままに、コ
ーディングシートに書いては訂正され、書いては訂正されるという作業が続く。この作
業には、精神的に参ってしまった。赤提灯に逃れ、アルコールで気炎を上げたくなる。
子供に学習をさせるのに、「ハイ、机の上に帳面を広げて」「ハイ、鉛筆を持って」
「ハイ、一ページ目の一行目、一コマ空けて、そこに Go と書きなさい」「その次は
一字空けて・・・・・・・・・」 というような授業しなければ、子供が動いてくれないといっ
た感じである。
電子の力を使って、目にも留まらない速度で計算する万能の機器と思っていた
コンピュータが、なんで、こんなに応用の利かない、「馬鹿」?!な機械なのか?と憤
慨する。
受講生同士で、そのような囁きが交わされる。
フォートランはまだしも、コボルとなるともっともっと手間のかかる指示をしなければ
動いてくれない。
長い研修の間、一度も本物のコンピューターを見る事も無ければ、触れた事も無
かった。ただ、プログラム作りの基本を、毎日毎日叩き込まれていた。
そのため、「今、俺は最先端のコンピューターを操作しているのだ」 といった実感は
無いまま、中央研修は終了した。
研修内容は良く分からなかったし、研修内容を教育研究所の研究生活で使うこと
も無く、忙しい毎日を過ごしている時、Basic が売り出された。
最初拝見して驚いた。 何でー! どうして! といった感じ。
適当な所に入力するだけで、即、コンピューターが動き、即、CRTに表示される。
表示位置の指定もしないのに、適当な所に文書が表示される。
これて何・・・?
我々が研修した事は一体なんであったの、と たまげる。
コンピューターの進歩の速さを、身をもって体験した瞬間であった。
あの長い苦しかった研修は、もう一切役に立たないし、次のパソコン活用に生か
されないのかと、暗然とする。
しかし、そんなチャンスを呉れた事。そして、長い研修生活を通じて良い友達が出来
たことには、感謝している。
その後、パソコンの進歩の速さは、驚異的なものである。
いまでは、写真が簡単に画面に取り入れられるし、その写真を自由自在に動かし、
加工までできる。
さらにCADでは、自分自身が映像の建物の中に入り、自由に動き回ることまで出来る。
その道のプロしか使えなかったパソコンが、会社・企業は勿論、一般家庭にまで
導入され、総ての国民がパソコンを簡単に利用出来る所まで進歩した。あの時の研修
を考えると夢のような話である。
この項終了
始めに 戻る